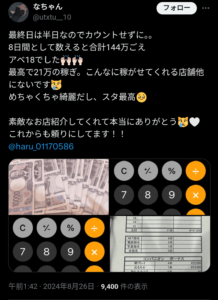【社会】こうして日本人の「新聞離れ」が進んでいった…「エモい記事」を大量に生み出した新聞記者たちの悲劇的な結末
【社会】こうして日本人の「新聞離れ」が進んでいった…「エモい記事」を大量に生み出した新聞記者たちの悲劇的な結末
■「全国紙」のビジネスモデルは終わりが近い
「新聞は商品なり」
私がかつて所属した毎日新聞を大きく発展させた戦前の名経営者、本山彦一の言葉だ。新聞はいよいよ危うい。日本新聞協会によれば、1世帯あたり部数はついに0.49部にまで下がり、毎日新聞は富山での配送休止を、日本経済新聞の一部九州エリアの夕刊休止という発表も続いた。
全国紙の発行部数は悲惨な状況にある。文化通信が報じた日本ABC協会の新聞発行社レポート(2024年上半期1~6月の平均販売部数)によると、2000年代初頭には1000万部超を誇った読売新聞は約595万部、朝日新聞は約343万部、毎日新聞は約154万部とゼロ年代と比べて半数以下になった。電子版が比較的好調な日本経済新聞も、ゼロ年代と比べて半数以下の138万部となっており紙版の減少分を代替するまでには至っていない。
「新聞紙」という商品の市場は拡大の兆しはなく、「全国紙」のビジネスモデルは終わりに近づいてきている。反マスコミ論者にとってみれば、朗報中の朗報といったところだろうか。
問題の多いマスメディアは潰れてもかまわない、というのは一つの筋だが私には喜ばしいこととは思えない。インターネットメディアが順調に発達して、人材育成まで担えるようになれば新聞が無くなったところでまったく困らないと豪語できたのだが、現実は紙以上にネットメディアの方がダメージは大きい。
■ネットメディアも新人育成を試みたが…
私はかつて「黒船」と呼ばれたアメリカ発のネットメディアに立ち上げから関わったことがあったが、日本ではわずか数年で報道部門は無くなった。端的にいえば収益化が難しくなったからだ。
インターネット「だけ」のニュースメディアで成長を遂げたところはほとんどと言っていいほどになくなった。そこに日本のメディアの危機がある。2010年代後半に、気鋭のインターネットメディアを率いた編集長は私にこんなことを言った。
「うちも新人を採用します。1回で終わらせず継続して取ろうと思っています。うちで本物のジャーナリストを育成できるか、それとも新聞のほうがうまく育成できるのか。そこは勝負ですね」
彼の構想は数年もしないうちにあっという間に崩れ去った。当時の新人は他社に転じてしまい、インターネットメディアで新聞社以上の規模での新人育成がうまくいったという話はまったく聞かない。
さらに言えば人材育成やスキルアップもなかなか難しい。
これも現状は、という注釈はつくがネットメディアから出てきた“ジャーナリスト”の記事はどうしてもオピニオン中心という傾向が強く、粘り強くファクトをとってくる技術に乏しいように思う。問題はそれだけではない。推測に推測を重ねたような緩い表現が横行し、情報の重みづけができておらず、陰謀論すれすれか過剰なオピニオンで売り物になる原稿が拡散していく。
新聞記者出身だからファクトベースになっているとは断言できないのは悲しいところだが、現状、新聞社が弱っていけば、その分だけ一から取材して何らかの形でアウトプットに繋げることができるジャーナリストの数は減る。どんな市場でも言えることだが、競争が弱まっていけば、技量を高めようというインセンティブも弱まる。
■「エモい言葉」はメディアをどう変えたのか
そんな時代にあって、新聞社が好転する道があるのか否か、私にはまったくわからないが、少なくとも陥ってはいけない道は見える。
まずシェア数、PV数、コミュニティ重視に陥って崩壊した10年代のネットメディアの模倣をしないことである。社会学者の西田亮介氏が朝日新聞のウェブサイトでそこまで「エモい記事」がいるのか? と問題提起をしたことが業界内で話題となったとき、思い出したことがある。
私は著書の中で、「エモい」という言葉を10年代に流行した象徴的な言葉と記したことがあった。10年代に一緒に働いていた若いライターたちがよく使っていた言葉で、彼らが指標としていたのは感情が突き動かされる「強さ」の度合いだった。「エモい」は褒め言葉で、人々の感情を刺激する強さが強ければ強いほど良いとされていた。
結果、何が起きたのか。人々の感情を刺激する「強い」言葉を選び、ライターもまたコミュニティの価値観を強く代弁し、常に正しく、強い言葉を使うようになった。そこに継続性はまったくなかった。
■新聞記者が強い刺激に引きずられてしまった
目の前にPV数やSNSでどの程度シェアされたかが表示されれば、人はそちらに引きずられていく。
エモい言葉で感情を刺激すればするほど、“平熱”の記事では届かなくなり、より強い言葉が求められるようなった。それはSNSを発火点にリベラルや保守といった党派性が強まっていく時代の先取りでもあったように思う。私はこれをネットメディアの悪しき慣習だと思っていたが、新聞記者たちもまた数字と感情に引きずられているという話をついに現場サイドからも聞くようになった。
その中で起きたのが「エモい記事」論争だとすれば、すべては納得できる。私はすべての新聞記事に、科学的なデータやエビデンスに基づく分析が必要だとは思わない。取材によって集めていく事実の中にはエビデンス、データが含まれることもあれば、現場を歩くことによってしか手に入れることができない人々の語りを中心に据えることもある。
しかし、どんな記事であっても曲げてはいけないことがある。ビル・コヴァッチとトム・ローゼンスティールが記した標準的なジャーナリズムの教科書『ジャーナリストの条件時代を超える10の原則』(澤康臣・訳、新潮社)に掲げられた「事実確認の規律」を守ることだ。これを緩めてはいけない。
■ジャーナリズムの基礎は「事実確認の規律」
彼らがはっきりと記しているように「結局は事実確認の規律が、ジャーナリズムと、エンターテイメントやプロパガンダ、フィクション、芸術とを区別する」からだ。あらゆるエンタメは何が最も人の気を引くかに重きを置き、プロパガンダは事実を恣意(しい)的に用いるか、でっち上げるかして自分たちを信じさせることだけに注力する。フィクションは事実を曲げてでも彼らが「真実と呼ぶもの」を感じ取れるように物語を練り上げるという一点において、ジャーナリズムと目指す地点が変わる。
ジャーナリズムは「起きたことを正しく捉えるためにどんなプロセスを経るか」を重視することによって、初めてオリジナリティを獲得する。
■明治期の新聞は“政治的”だった
とはいえ、規律を徹底するだけでビジネスが好転すると語るには厳しいのが日本の現状だ。
これは簡単に記すが、経営という観点、そして会社としての新聞社にとって必要なのは、紙の代替を正しく諦めることだろう。電子版に置き換える努力は必要だが、限界はある。それよりも新聞以外で稼げるモデルを見つけたほうが生き残りへの道は切り開けるかもしれない。
ヒントになるのが冒頭の言葉だ。本山は現代的に言い換えると新聞社そのものがビジネスの主体となり、その価値を高めるに何がありえるのかを考えていた。
経済誌『エコノミスト』(毎日新聞出版、1998年3月24日号)に掲載された前坂俊之氏による評伝「『エコノミスト』を創った新聞界の巨人 フィランスロピーの先駆者だった」を基に本山の経歴を簡単に振り返ってみよう。
本山は福澤諭吉の門下生で、福澤が創刊した『時事新報』総編集、民間のビジネスパーソンに転じ、大阪の藤田組で児島湾開墾事業に携わった。今の毎日新聞の源流とも言える大阪毎日新聞の相談役に就任したのは1889年で、1903年に社長に就任した。彼が掲げたのが独立自営、不偏不党だった。
この言葉には少しばかり注釈が必要だろう。明治期の新聞は、今とは比べ物にならないくらい“政治的”だった。当時、かなりの売れ行きを誇った国民新聞は藩閥勢力とつながりが深く、報知新聞——今はスポーツ紙にその名を残している——は大隈重信が率いた改進党系の政党に近い論陣を張るといったように、各社は論で競った(当時の新聞の傾向は神戸大学付属図書館のサイトに概要が整理されている)。
■ネットメディアの失敗を後追いするべきではない
本山が掲げた不偏不党は古巣の時事新報と同じように、どこか特定の勢力に肩入れすることないという宣言くらいに受け取っていいだろう。そして、そのために大事だったのが独立自営、つまり自前で稼ぐということだ。そのために彼は広告に力を入れ、写真広告、記事広告などを初めて設け、広告を増やすことで経営を安定させた。後年は週刊誌という新しいメディアも立ち上げて、事業を拡大した。
自由な言論空間を作るにはビジネスの主体となり、収益を得ることがなにより重要な要素だった新聞において記事が大事であることは論を俟(ま)たないが、稼げる方法を模索する責任が経営陣にはある。自分たちで難しいのならば、外の目を入れることも必要だろう。
いずれにせよ、インターネットのメディア空間は新聞社の代替にはなりえないなかで、まだ新聞社の社会的役割は残されている。
インターネットを開けば、複雑な事実確認の規律が緩みきって、かつエモーショナルな「政権は〜〜に支配されている」「〜〜が黒幕にいる」といった言葉が溢れているが、それこそ規律の徹底には技量が必要となることの証左だろう。感情やわかりやすい「ストーリー」、煽ったタイトル、社会運動家のような正しいオピニオンは一時の数字は確かに稼ぐ。だが、それは10年代ネットメディアの失敗を後追いすることとイコールで結ばれ、やがてジャーナリズムのオリジナリティは消失する。
新聞が率先して後を追ってはいけない。ジャーナリズムの基本に基づいた「強い」記事を出し続けられるだけの独立自営を貫き、次世代に技量を伝承するメディア企業であってほしい。
10年代に手痛い失敗を経験した私が、今思うことである。
———-
記者/ノンフィクションライター
1984年、東京都生まれ。立命館大学卒業後、毎日新聞社に入社。2016年、BuzzFeed Japanに移籍。2018年に独立し、フリーランスのノンフィクションライターとして雑誌・ウェブ媒体に寄稿。2020年、「ニューズウィーク日本版」の特集「百田尚樹現象」にて第26回「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」作品賞を受賞した。2021年、「『自粛警察』の正体」(「文藝春秋」)で、第1回PEP ジャーナリズム大賞を受賞。著書に『リスクと生きる、死者と生きる』(亜紀書房)、『ルポ 百田尚樹現象』(小学館)『ニュースの未来』(光文社)『視えない線を歩く』(講談社)がある。
———-