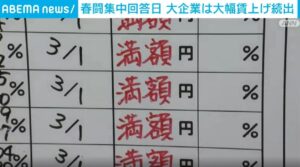「修学旅行がつまらない」と親からクレームが…家庭や学校を蝕む「子どもを不快にさせない」という危険な風潮
「修学旅行がつまらない」と親からクレームが…家庭や学校を蝕む「子どもを不快にさせない」という危険な風潮
「修学旅行がつまらない」と親からクレームが…家庭や学校を蝕む「子どもを不快にさせない」という危険な風潮 | ニコニコニュース
※本稿は、藪下遊、髙坂康雅『「叱らない」が子どもを苦しめる』(ちくまプリマ―新書)の一部を再編集したものです。
■「なかなか変わらない」ことには理由がある
学校は「惰性が強いシステム」です。入力から出力までに時間がかかるということであり、つまり教育に対して、何かしらの働きかけをしても「なかなか変わらない」ということになります。この点は不登校への対応や、学校で起こるさまざまな問題への対処の遅さとして批判されがちですね。
一斉教育には問題があるのになかなか改善されないとか、多様性を認める形になっていないとか。ですが、学校が「惰性が強いシステム」になっているのには、ちゃんと理由があります。
社会状況がどれだけ変わっても、世の中がどんなに混乱したとしても、学校は「そう簡単に変わるわけにはいかない」のです。社会状況や世の中の雰囲気で学校がころころ変わってしまえば、次世代を担う子どもたちに「安定した教育」を提供することができなくなります。
教育というのは水などと同じ社会的共通資本ですから、どんなに社会が混乱しようが、天変地異が起ころうが「一定以上の質のものを提供し続ける」ことが重要です。社会全体が安定的成熟を得るために、教育は「そう簡単に変わらないもの」「そのように設計されている制度」なんです。ただ、そんな「惰性の強いシステム」を備えた学校でさえ、ここ数十年の間で少しずつ変わってきています。
■子どもの「特徴・特性」には踏み込まなくなった
例えば、通知表一つとってもこの50年くらいでかなり内容が変わっています。
50年前の通知表は、かなり子どもの問題点を指摘する形で記述されていましたが、最近ではそういった内容を書くことはまったくありません。学校が「子ども個人の特徴・特性について、批判的に明示すること」は皆無になったと言ってよいでしょう。
他にも色んなことが変わりました。成績が貼り出されることはなくなったし、食べられない給食を前にずっと残されるということもなくなりました。昔から変わらず存在していた「宿題、やったけど忘れてきました」という子どもには「じゃあ、明日持ってきてね」で終わりです。下手に「本当はやってないだろう」などと言えば、たちまち親から「うちの子が嘘(うそ)をついたというのか」と電話が入ります。
私はかつて肥満体型でしたが、通っていた小学校では男女問わず肥満体型の子どもだけ給食時間に集められて食べ方指導をしていました。今の時代だと考えられない話ですよね。このように、子どもの「特徴・特性」に対して、ずかずかと学校が踏み込んでくることがなくなり、証拠が無いことについては追及せず、子どもが不快に感じるような関わりを学校は相対的にしなくなりました。
■「子どもを不快にさせる」ことが忌避されている
このような「学校の変化」は学校単体で生じることは決してありません。
社会からそうした「入力」が絶えずなされているからこそ、学校という「惰性の強いシステム」でさえ変わってきたと考えるのが妥当です。すなわち、社会全体に「子どもを不快にさせる」ということへの忌避感・嫌悪感が広がっており、それを受けて学校というシステムでさえ変化してきたというわけです。
ただ、本当に「子どもを不快にさせる」ということが問題なのでしょうか?
「子どもの不快」は反応の仕方の一つに過ぎません。その「不快」がどういったしくみで生じているのかを考えて接することが重要であり、「不快」だから不快にした人が悪いとか、「不快」を除かねばならないというわけではないはずです。子どもが感じる不快をきちんと見分けていくことは、とても大切なことです。
見分ける必要のある不快の一つは「要らない不快」です。体験することに何の意味もない不快であり、例えば、いじめられること、人格を軽んじられること、暴力を受けることなどです。こういうものは、できる限り自分に降りかからないようにすることが大事であり、そういう状況を避けたり、逃げたりすることが大切です。
■「修学旅行がつまらない」というクレームが入ることも
もう一つは「成長のための不快」です。それを経ることで成長につながるような不快であり、例えば、間違っていることや悪いことを指摘される、自分の限界に気づかされる、他者との意見の違いを経験するなどです。こういう不快については、受けとめ、自分の中で消化していくことが重要になります。
【事例1:修学旅行中に担任に電話する母親】
不登校気味の高校二年生女子の母親。修学旅行中に担任に対して「娘が面白くないとメールしてきた。何とかしてあげてください」と連絡してくる。
修学旅行中は人間関係の交錯が起きやすい(自由時間に誰と回るか、バスで誰が隣か、班の一人が戻ってこない……など)ので楽しいばかりではないのが普通です。ただ、こうした人間関係の交錯が起こることによって子どもたちが成長する機会となるのも事実です。
しかし、この事例の母親は子どもが不快であることをとことん排除しようとして、かなり非常識な行動を取っています。母親が「子どもの不快に過敏に反応する」からこそ、子どもが母親に「面白くない」と連絡したのだと思いますし、これまでも「不快の主張」によって母親を操作して環境を変えてきた可能性も考えねばなりません。
■「褒めて伸ばす」が勘違いされている
子どもが不快だからといって、不快が生じるあらゆる状況を排除・操作してしまえば、成長に欠かせないような出来事を「要らない不快」と考えて回避してしまい、せっかくの成長の機会が失われることになってしまいます。
また、社会の中で自分が失敗したことを指摘されて「パワハラ」と言ったり、相手が思った通りにしてくれないだけで「あの人はおかしい」と言ったりしていれば、当然、成長することも、自分以外の人が「思い通りにはならない」という当たり前の感覚が身につくことも起こらなくなります。
「子どもを不快にすることへの拒否感」と関連がありそうな社会の風潮として「褒めて伸ばす」があります。社会の中でかなり市民権を得ているように見える「褒めて伸ばす」という子育ての在り方ですが、カウンセリングで多くの家庭を見る中で「褒めて伸ばしている」つもりが、いつの間にか「子どもの問題を指摘しない」「ネガティブなところを示さない」という形に変質してしまっていることがあります。
本来、「褒めて伸ばす」とは、「ネガティブな面は見せない」ということではないはずです。ポジティブなところだけを伝えて褒めるのに、ネガティブなところを無かったかのように振る舞うということは、子どもを根っこの部分では弱い存在だと見なしているのです。
無自覚のうちに「ネガティブなところを示すとショックを受けて立ち直れないだろう」「この子にはそんなパワーはないだろう」と子どもの力を低く見積もっているからこそ、子どもがショックを受けるような情報を誤魔化したり加工したりするのです。
■そもそも大人が子どもを信頼できていない
こうした「現実の加工」を子どもへの「優しさ」と考えるのは、周囲の大人が抱えている「子どもを信じることができない弱さ」への言い訳です。自己肯定感という言葉があります。定義は色んな人が色々言っていますが、ここでは文字通り「ありのままの自分を肯定する感覚」と思っていただいて問題ありません。
人間にはポジティブな面もあれば、ネガティブな面もあるのが当たり前です。このいずれに対しても「自分の大切な一部だ」と思えること、そういうネガティブな面を持つ自分であっても「肯定することができる」という実感を指して「自己肯定感」と呼ぶのです。
前回の記事でも紹介した「世界からの押し返し」とは、こういうネガティブな面もきちんと子どもに示していきましょう、そして「関係性の中で不快感を納める」とはネガティブな面がある子どもであっても「そういうあなたが大切だ」「そんなあなたと生きていく覚悟がある」ということを伝えていきましょう、ということなんです。
同じく「子どもを不快にすることへの拒否感」と絡んできそうな社会の風潮に「やりたいことを大切にする」というものがあります。一見すると「やりたいこと」で生きていくのは素晴らしいことのように思います。ですがこの風潮も、「やりたくないことはしなくていい」という形に変質してしまうリスクがあることを忘れてはいけません。
■「やりたいこと」は他者を必要としない
マンガ『ONEPIECE』の第一巻で主人公のルフィが出港の際に、たった一人船の上で「海賊王に俺はなる!」と叫びます。まさに「やりたいこと」を叫んでいるわけですが、こうした「やりたいこと=願望」には、他者を必要としないという特徴があります。願望はあくまでも個人の思いであり、他者の存在は本質として重要ではありません。誰かから承認されなくても、「○○をしたい」という願望は持つことができますからね。
これに対して「できること=可能」は他者の存在が必要です。「○○ができます」と言うときには、その「○○」を必要としている人がそばにいることが前提です。
私は一応「カウンセリングができます」と言えますが、この言葉は「カウンセリングを必要としている人」が存在するからこそ成り立つものなんです。一人でシャワーを浴びているときや、布団に入るときに「私はカウンセリングができます」とは言いません。そこには他者が存在しないのですから。
■子ども時代は「できること」を開拓していく時期
こうした「願望」と「可能」の間には、「子ども」と「大人」を分岐する境界線があると内田樹先生は述べています。
大人というものは、自分が何者であるか、自分がこれからどこに向かって進んでゆくのか、何を果たすことになるのか、ということを「自分の発意」や「独語」の形ではなく、「他人からの要請」に基づいて「応答」という形で言葉にする人のことを指すのであり、これこそが「人間の社会」が始まる基本条件のようなものであるとしています。
そもそも子ども時代というのは「できること=可能」を開拓・拡大していく時期です。自分は何ができるのか、為(な)すことができる範囲はどの程度か、そういうことを知る時期なんです。だからこそ、学校を始めとした社会の中では、子どもに「まだ知らないこと」を教えるし、「できないこと」でも頑張ってやってもらおうとするわけです。
そういう活動を通して、子どもの「可能」を開拓・拡大するというのが学校の機能の一つなんです。この時期に「やりたいこと=願望」を中核にしてしまうと、可能の範囲を知らずに「できる」と勘違いしたり、未知のものを「やりたくない」と子どもの快不快だけを基準にして排除してしまう恐れがあるのです。
■「不快にさせない風潮」が社会に蔓延してしまった
子どもを不快にすること、褒めて伸ばすこと、願望で判断させること。互いに関連がありそうな社会の風潮ですが、これらの考え方が誤解されたり、都合よく改変されたり、極端に偏ることで、子どもの成長を阻害する可能性があることを述べました。
成長に必要な「不快に耐える肺活量」を持つことで子どもたちが「昨日の自分」よりも成熟すること、できないことを共有して「どんな自分でも、これが自分だ」と思えること、知らないことやできないことに取り組むことで「可能の範囲」を増やすことなどはすべて、子どもが社会的に成熟する上で欠かせないことのはずです。
しかし社会では、子どもを不快にすることを避け、できない自分を棚上げし、「やりたくないことはしない」というマインドが育つような風潮が中心になりつつあります。
こうした風潮が強くなってきているのは、今までの社会が子どもを抑え込んできたことへの揺り戻しなのか、養老孟司(ようろうたけし)先生が述べるような「西欧近代的自我」が導入されたこと(唯一無二の「自分」があって、それは本質的に変わらない。だからそれを尊重しなければならない。周りも認めねばならない。阻害するのはおかしい。という感じ)が関連しているのか、確実なことは言えませんがさまざまな背景がありそうです。
いずれにせよ、本稿で紹介したような子どもたちの不適応の増加は、こうした社会の風潮が学校や家庭にまで降りてきていることによって生じたと私は推測しています。
【参考・引用文献】
内田樹(2008)『街場の教育論』ミシマ社
内田樹(2017)『困難な成熟』夜間飛行
養老孟司(2023)『養老孟司の人生論』PHP文庫
———-
スクールカウンセラー
1982年生まれ。仁愛大学大学院人間学研究科修了。東亜大学大学院総合学術研究科中退。博士(臨床心理学)。仁愛大学人間学部助手、東亜大学大学院人間学研究科准教授等を経て、現在は福井県スクールカウンセラーおよび石川県スクールカウンセラー、各市でのいじめ第三者委員会等を務める。共著に『「叱らない」が子どもを苦しめる』(ちくまプリマ―新書)がある。
———-
———-
和光大学現代人間学部教授
1977年生まれ。筑波大学大学院人間総合科学研究科心理学専攻修了。主な著書に『恋愛心理学特論――恋愛する青年/しない青年の読み解き方』(福村出版)、『深掘り!関係行政論 教育分野 公認心理師必携』(北大路書房)、『公認心理試験対策総ざらい 実力はかる5肢選択問題360』(福村出版)、『本番さながら!公認心理師試験予想問題 厳選200』(メディカ出版)、共著に『「叱らない」が子どもを苦しめる』(ちくまプリマ―新書)などがある。
———-

 |
ゲスト 我慢させる厳しさは教育として必要だって、古くからそう言われて来たのには意味があるって事を真面目に見直せ。変えていく事こそ正しいと妄信して考え無しに何でも教育に適用していこうとする無責任な奴ら。結果、社会に失敗を負わせる事になっても責任なんて取らない、昭和かよと言ってりゃ正当性が得られると思ってる単細胞生物。 |
 |
2kg 楽しいどうのより、本来なら修学したいことを予算から交通手段、ルートや時間を生徒に決めて調べてってやらせて初めて教育になるものを、ただの学校行事で業者と癒着あるような意味わからんのにしてる点があるからな。生徒数がもっと減って、修学旅行の予算増えれば解決するんじゃない? |
The post 「修学旅行がつまらない」と親からクレームが…家庭や学校を蝕む「子どもを不快にさせない」という危険な風潮 first appeared on カリスマニュース速砲.